労災保険と雇用保険の2つを「労働保険」といいます。労働保険は、雇われて働く人の業務上傷病や失業に備える公的保険で、労働保険を成立させる(=従業員を雇用する事業所の存在を公的機関に届け出る)ことは事業主の義務です。

労働保険|強制適用事業所の要件
労災保険(労働者災害補償保険)は、原則として従業員を雇用する全ての事業主に加入義務があります。(例外:個人経営で労働者数5人未満の農林水産の事業)
雇用保険は、次の要件の従業員を雇い入れた場合に必要です。
・週の労働時間が20時間以上、かつ
・31日以上の雇用見込みがある
労働保険の成立手続き
最初の従業員を雇い入れたときは、次の手続きをする必要があります。
・保険関係成立届
・概算保険料申告書
・雇用保険適用事業所設置届
・雇用保険被保険者資格取得届
順に説明しましょう。
保険関係成立届|労災保険と雇用保険
「保険関係成立届」は、労働保険(労災保険と雇用保険の一方または両方)の適用事業所であることを届け出る手続きです。雇用保険に加入しないパート(例えば週の所定労働時間が10時間など)のみを雇ったときも労災保険には加入させる必要があるため、保険関係成立届の提出が必要です。
| 提出書類 | 保険関係成立届 |
| 添付書類 | ・会社謄本(個人事業の場合は事業主の住民票) ※所在地が登記簿と異なる場合は賃貸借契約書の写し等 |
| 提出先 | 事業所所在地を管轄する労働基準監督署 |
| 提出期限 | 保険関係成立日の翌日から10日以内 |
・事業所の所在地とは実際に従業員が働いている場所のことで、必ずしも会社謄本に記載されている本店所在地とは限りません。
・「雇用する従業員数」は、見込み人数で構いません。
・「事業の種類」は、労災保険料率に関係するため、注意して記入してください。「労災保険率適用事業細目表」を参考にするとよいでしょう。
保険関係成立届を提出すると「労働保険番号」の入った控を返してくれます。この控は雇用保険の手続きに使用します。
「保険関係成立届」の用紙は、労働基準監督署、ハローワーク、労働局などで入手できます。「保険関係成立届」と一緒に「概算保険料申告書」の用紙も入手しておくとよいでしょう。
ところで、用紙をもらうとき、窓口で「一元ですか?二元ですか?」と尋ねられることがあります。二元適用になるのは、建設業・農林水産業など一部の事業です。一元か二元か不明な場合は、窓口で業種を告げ、教えてもらいましょう。
概算保険料申告書の提出と納付
概算保険料申告書とは、その年度の労働保険料の見積額を申告する書類です。労働保険料とは、労災保険料と雇用保険料のことです。概算保険料は「その年度の賃金見込み額」に労災保険料率と雇用保険料率を乗じて算出します。
最初の従業員を11月に雇い入れた場合、11月から翌年3月までの賃金見込み額に、労災保険料率と雇用保険料率を乗じることになります。
| 提出書類 | 概算保険料申告書 |
| 添付書類 | なし |
| 提出先 | 事業所所在地を管轄する労働基準監督署・労働局・日本銀行等 |
| 提出期限 | 保険関係成立日の翌日から50日以内 |
労働保険関係成立届と概算保険料申告書は、窓口・郵送・電子申請のいずれの方法でも提出できますが、不慣れな場合は窓口に提出するとよいでしょう。記載間違いなどがあっても、その場で訂正してもらえます。
手続きに慣れてくると電子申請が便利です。電子申請であれば、窓口に行く時間も郵送料金もかかりません。
雇用保険適用事業所設置届
雇用保険適用事業所設置届は、会社自体を雇用保険の適用事業所にする手続きです。
| 提出書類 | 雇用保険適用事業所設置届 |
| 添付書類 | ・労働保険関係成立届の控コピー ・会社謄本(個人事業の場合は事業主の住民票) ※所在地が登記簿と異なる場合は賃貸借契約書の写し等 |
| 提出先 | 事業所所在地を管轄するハローワーク |
| 提出期限 | 事業所を設置した日の翌日から10日以内 |
雇用保険適用事業所設置届を提出すると「適用事業所台帳」が交付されます。この適用事業所台帳は、雇用関連助成金などの申請時に添付することがあるため、大切に保管しておきましょう。
雇用保険被保険者資格取得届
雇用保険被保険者資格取得届は、従業員個人を雇用保険に加入させる手続きです。
| 提出書類 | 雇用保険被保険者資格取得届 |
| 添付書類 | 出勤簿 その他賃金台帳を雇用契約書を求められることがあります |
| 提出先 | 事業所所在地を管轄するハローワーク |
| 提出期限 | 雇い入れ日の翌月10日まで |
雇用保険被保険者資格取得届が受理されると、雇用保険証と雇用保険資格取得確認通知書が交付されます。
参考:労働保険料はどのくらい?
労働保険の成立手続きをすると、概算保険料を納付しなければなりません。おおよそいくらくらいになるか、ご参考のために紹介します。
労災保険は、業種により、2.5/1000から88/1000まで(2025年度)料率が異なります。労災保険は、全額を事業主が負担します。
雇用保険は「一般の事業」「建設の事業」「農林水産・清酒製造の事業」で料率が異なります。
一般の事業の場合は、14.5/1000(事業主負担分9/1000、被保険者負担分5.5/1000)です。(2025年度)
事例:
・飲食店(労災保険料率 3/1000)
・従業員数 1名(月給300,000円、通勤費込み、賞与なしの予定)
・フルタイム勤務、5月1日に雇い入れ
雇入れ日から翌年3月までの賃金 300,000円×11ヶ月=3,300,000円
3,300,000円×(労災保険料率3/1000+雇用保険料率14.5/1000)=57,750円
このケースでは、概算保険料は 57,750円になります。
※おおまかな保険料額をご紹介するために細かく計算しましたが、概算保険料は見込み額を記載すれば足りるため、厳密に計算しなくても受理されます。
労働保険の届出をしないリスク
労働保険の成立をいつまでも怠っていると、行政官庁の職権で成立手続きが行われ、労働保険料も認定決定されます。そして認定決定された労働保険料は、自分で申告するよりも多額なことが多いのです。更に遡及分の労働保険料(2年分)と追徴金も徴収されます。
また、故意または重大な過失により保険関係成立届を未提出だった期間に労災事故が発生した場合は、労災保険の給付費用の全部または一部が事業主から徴収されることになります。
雇用保険については、従業員の入社日に遡って取得手続きをしなければなりません。入社から時間が経っている場合、添付書類を揃えるだけでも大変な手間がかかるでしょう。
労働保険の成立手続きをしていないと、金銭的な損失だけでなく周囲の信用にも影響します。そうしたことにならないよう、滞りなく手続きを済ませることが大切です。
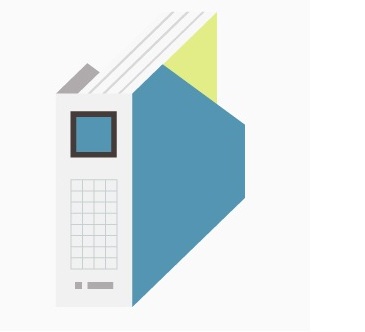
新規適用届の書き方、概算保険料の算定、雇用保険適用事業所設置届の地図の書き方などに迷ったときは、社会保険労務士にご相談ください。
→お問合せはこちらです
参考資料:
厚生労働省 令和7年度の労災保険率について
厚生労働省 令和7年度の雇用保険料率について


