テレワークや出張など社外で労働させる場合、会社が労働時間を把握しづらいことがあります。そうした時に活用できる制度が、労働基準法第38条の2に定められた「事業場外みなし労働時間制」です。

社屋の中で働く従業員は、タイムカードで始業終業の時刻を把握し、上司の目視により就業事実の確認もできます。しかし会社の外で働く従業員の中には、会社からの随時の連絡や指揮命令ができず、労働時間管理も困難な人もいるでしょう。そうした場合に、事業場外のみなし労働時間制が用いられます。
みなし労働時間は何時間?|労働基準法
みなし労働時間制のもとで「何時間、働いたものとみなすか」については、労働基準法第38条の2に下表のように定められています。
| ケース | みなす時間 |
| みなし労働時間が所定労働時間を超えない場合 | 所定労働時間 |
| その業務を遂行するために所定労働時間を超えて働く必要がある場合 | その業務の遂行に通常必要とされる時間 |
| 上記で労使協定をした場合 | 労使協定※で定めた時間 ※届出が必要 |
e-Gov法令検索 労働基準法 条文により表を作成
なお、業務遂行のために必要な時間が法定労働時間を超える場合は、1.25倍の割増賃金が必要です。例えば、みなし労働時間が10時間の場合は、法定労働時間(8時間)を超える2時間分の割増賃金が必要になります。
みなし労働時間制が適用できないケース
従業員が事業場外で働いている場合でも、会社が労働時間を把握できる場合は、事業場外みなし労働時間制は使えません。
以下は、みなし労働時間制が適用できないケースについての通達による事例です。
・何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、メンバー中に労働時間の管理をする者がいる
・ポケットベル等によって、随時、使用者の指示を受けながら労働している
・事業場において、訪問先、帰社時刻、当日業務の具体的指示などを受け、事業場外で指示通りに労働し、その後事業場に戻る場合(以上、昭和63年1月1日基発第1号)
事業場外と事業場内が混在しているとき
事業場外で働いた後、会社に戻って内勤もするような場合は、内勤時間については別途把握しなければなりません。この場合は、事業場外労働の「みなし時間」、社内の「別途把握した時間」を合算して実労働時間とします。(昭和63年3月14日基発150号)
濫用を避けて適用は慎重に|みなし労働時間制
みなし労働時間は便利ですが、実際に労働時間を把握できる従業員には適用できない制度です。みなし労働時間制の使い方を誤ると、残業代の未払いで是正勧告や訴訟につながることがありますので、濫用を避けることが大切です。
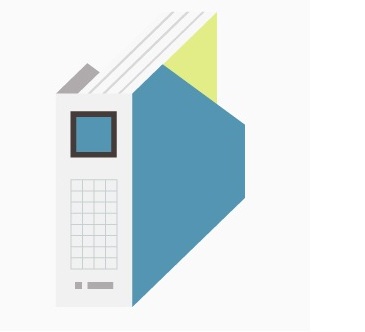
制度の誤った適用は、未払い残業や是正勧告などのリスクにつながります。
みなし労働時間制の適用の可否、協定の締結方法に迷ったときは、お気軽に社会保険労務士にご相談ください。
→お問合せフォームへ
参考資料:
e-Gov法令検索 労働基準法 第38条の2
厚生労働省 「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適切な把握のために
厚生労働省 Q&A


