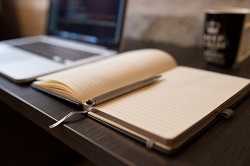会社経営を続けていると、従業員を解雇せざるを得ないときもあるかと思います。
しかし解雇は自由にできるものではなく、法律上のルールに従って行う必要があります。
解雇予告と解雇予告手当
従業員を解雇するときは、原則として下記1~3のいずれかの方法を採らなければなりません。
普通解雇だけでなく、整理解雇や懲戒解雇(一定の重責解雇を除く)の場合も同様です。
1 30日以上前に解雇の予告をする
2 解雇予告手当として、30日以上分の平均賃金を支払う
3 上記1と2を併用する
それぞれについて、説明しましょう。
30日以上前に解雇予告をする
従業員を解雇するときは「解雇日の30日以上前」に、その旨を本人に告げる必要があります。
この「30日」は暦日でカウントします。そのため、土日などの公休日を含めて30日前に予告すれば足ります。
なお「解雇予告をした日」は「30日」に算入しません。予告日を除外し、翌日からの期間で「30日」を確保する必要があります。つまり、6月30日付で解雇したい場合は、遅くとも5月31日のうちに、解雇の申し渡しをしなければなりません。
解雇の申し渡しは、口頭でも有効です。しかし後々のトラブル回避のためには、書面を作成した方がよいでしょう。
解雇予告手当を支払う
30日前に解雇予告をしなかった場合でも。解雇予告手当を適正に支払えば、有効に解雇ができます。解雇予告手当の額は「平均賃金の30日以上分」です。
解雇予告手当は、解雇の申し渡しと同時に支払う必要があります。そのため「予告手当は最後の給料に上乗せするからね」といった方法は、原則としてNGです。
解雇予告と予告手当の併用
30日前に解雇予告ができなかった場合でも、解雇予告と解雇予告手当の支払いを併用することで、有効に解雇できます。解雇予告手当を支払った日数分だけ、解雇予告の日数を短縮することが可能なのです。
つまり10日後に退職してほしい場合は「10日前に解雇予告を行い、その際に20日分の解雇予告手当を支払う」ことになります。
解雇予告が除外されるケース
ただし解雇予告や解雇予告手当の支払い義務が除外されることがあります。それは、以下のようなケースです。
・試用期間中の労働者を、雇入れから14日以内に解雇する場合
・次の1または2に該当し、労働基準監督署の解雇予告除外認定を受けた場合
1 天災事変その他やむを得ない事由により、事業の継続が不可能である
2 労働者の責めに帰すべき重大な事由が存在する
予告手当と社会保険料・所得税
解雇予告手当は「賃金」ではなく、社会保険料の対象にもなりません。
解雇予告手当の税法上の扱いは「退職所得」です。そのため源泉徴収税は、給与所得ではなく退職所得の税率で差し引きます。
解雇する従業員から「退職所得の受給に関する申告書」が提出されていない場合は、原則として20.42%の所得税を源泉徴収する必要があります。ただし提出されている場合は、退職所得控除(最低額が80万円)が適用されます。この場合は、源泉徴収税額がゼロになることも少なくありません。